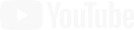漆芸家や塗師、文化財修復職人などからも高く評価される国産最高級品
今回は、国産漆の最大産地・岩手県二戸市の「浄法寺漆」をご紹介します。
浄法寺漆の歴史
浄法寺の縄文遺跡から赤い漆が飾りについた石刀が発見されました。それがこの地での最初のうるしです。まだ縄文時代のことは多くは解明されていないですが古くから漆が身近にあったことが伺えます。
次に歴史に現れるのは「浄法寺塗」。その起源は、平安時代にまで遡ります。728年(神亀5年)に行基が聖武天皇の名を受けて開山した「八葉山天台寺(はちようざんてんだいじ)が発祥と言われています。天台寺開山の際に派遣された僧侶たちが、自らの什器(じゅうき)を作るために漆工(しっこう)技術を持ち込んだことが始まりで、やがて僧侶たちが作った漆器を参拝者に供するようになりました。漆器とともに漆塗りの技術も庶民に伝わり、庶民用が普段使いに使用する「御山御器(おやまごき)」として天台寺周辺に広まったと言われています。「御山御器」は装飾のほとんどない、素朴で実用的な普段使いの器です。現在に続く浄法寺塗の特徴は、質素倹約を旨とした寺の生活が育んだものだったと言えます。地元には今も古い時代に用いられた漆器の呼称として、飯椀・汁椀・皿の三ッ椀を指す「御山御器」の名前が残り、天台寺との深い関わりを伝えています。ただし、浄法寺地域での漆掻きの開始が記録として残されているのは、江戸時代からです。
もともと、浄法寺やその周辺地域は漆の木が豊富な地であり、そんな背景が浄法寺塗の発展に寄与したことは想像に難くないでしょう。藩政時代、漆は盛岡藩の貴重な産物でしたが、藩全体の約47%が浄法寺を含む二戸地域からの産出だったとの記録が残っています。江戸時代になると南部家盛岡藩の統制下、この地方に漆掻奉行が置かれ、漆は他領へ持ち出すことを禁じられていました。
明治時代に入ると、古くから漆掻き職人の多かった福井県今立地方からの出稼ぎ職人が岩手へと進出してきます。「越前衆」と呼ばれた彼らは、それまでの木を長く生かしながら樹液や実をとる「養生掻き」に変わり、より多くの樹液を得ることができる「殺し掻き(木はその年には切ってしまう)」を広めたほか、漆掻きの道具をこの地にもたらしました。漆生産量の増加にも伴い、「庶民の漆器」である浄法寺塗の需要は大正・昭和にかけて高まり、その販路は海外にまで広がって行きました。
時代は進み、太平洋戦争の頃に漆は国の統制品となり、その全ては国に納められることとなります。また戦後間もない物資が乏しい時代には、限られた量の国産漆は高値で売買されました。図らずも、先の大戦は浄法寺漆に盛況の時代をもたらしました。しかし戦後、復興が進むと、時代や生活様式の変化、価格の安い輸入漆の増加に伴い、浄法寺塗は衰退し、困難な時代を経ることになります。
やがて、昭和期から平成期にかけて、岩手県の中尊寺金色堂、京都府の金閣寺、栃木県の日光東照宮・二荒山神社・輪王寺といった、世界遺産・国宝級の文化財の修復に用いられる新たな需要が生まれました。文化庁は2015年2月、国宝や重要文化財を修繕する際は国産漆を使うよう通知しました。文化庁の推定によると、必要な国産漆は年2.2トンで、現状の国内生産量(1.2トン)はその半分程度しかありません。浄法寺地域に昭和20年代には300人あまりいた漆掻き職人も平成期に入ってからわずか20人程へ減少しており、職人の高齢化も著しく、漆の苗木も不足気味となっています。 そこで二戸市は2016年度、志望者をいったん市職員として採用し、数年かけて漆掻き職人に育てる「うるしびと」制度を設け、20~40歳代の応募者が修行している。また市内で約15万2000本まで減った漆の植樹も奨励しています。「日本うるし掻き技術保存会」は、国の選定保存技術「日本産漆生産・精製」技術の保存団体に認定され、文化庁の支援を受け、若手研修生への指導を実施しています。
浄法寺漆の特徴
「浄法寺漆」は、硬化後の強度が非常に優れているうえに、安定した品質を有する漆です。透明度、硬化時間、粘度等のバリエーションが豊富といった特徴があるとともに、耐久性にも優れていることから、漆芸家や塗師、文化財修復職人などから高く評価されています。
また、漆は、単に塗料としてだけでなく、風雨や外気にさらされる材木の劣化を防止する役割も果たしています。鹿苑寺金閣の修理の際に、世界中の良質と称される漆と塗膜などの比較試験がおこなわれ、硬化後の強度が非常に優れている「浄法寺漆」が採用されました。
日本の四季の変化に対応できる「浄法寺漆」は、日本の文化や歴史を支える素材として古くから国宝や重要文化財の修理・修復には欠かせない貴重な地域資源であり、最近では、新年恒例の一般参賀など特別な日にのみ開く皇居正門の改修や世界遺産である「日光の社寺」の平成の大修理など、多くの日本を代表する建造物の修理・修復に使用されています。
日本のウルシの栽培面積は326ha、その約85%にあたる278haを岩手県が占めています。生産地では、岩手県浄法寺漆生産組合を中心に、行政や、漆生産者などの関係者が一体となって、ウルシの木の植栽・育成のほか、漆掻きの技術伝承に取り組んでいます。地域には、伝統的な漆掻きの技術を習得した専業の職人が20名ほどおり、職人それぞれの個性や技術を活かした豊富なバリエーションの漆を生産しています。
優れた漆掻き技術とウルシ林を引き継ぐことで、「浄法寺漆」の生産地は、国内で流通する国産漆の7割を生産しています。日本国内で使用される漆の98%以上を中国からの輸入に頼る中で、浄法寺漆は、日本一の生産量と高い品質を誇っています。
浄法寺漆の普及について
「浄法寺漆」の活性化のため、ブランド化と普及に取り組んだ企業があります。(株)浄法寺漆産業は、プラスチック製チューブ入りの浄法寺漆を開発しました。通常は原液をそのまま漆器の産地に出荷しますが、精製することで付加価値を高め、小分けで使いやすくしました。商品は11年にグッドデザイン賞を受賞、海外の文具メーカーや美術館などから引き合いが相次ぎました。
その後、デザインにこだわった漆器を開発、販売する一方、PRのため各地で同社社長が講演をしました。価格が中国産の約5倍するため高級品での利用も提案しました。浄法寺漆で自動車の内装を手掛けたり、JR東日本の豪華寝台列車「トランスイート四季島」のパネル壁材に採用されたりさまざまな分野で採用実績が広がっています。
15年2月、文化庁が国宝などの修復は国産漆限定と通知したことで、国産漆の環境は激変しました。修復用で年間2.2トン、漆器などの利用も含めると計3.2トンが必要になるとみられますが、浄法寺漆の生産量は約0.9トンで、国産漆全体でも約1.2トンに留まります。
同社は国産漆普及のために増産しようと、17年から岩手県一関市で原木の産地づくりに取り組み始めました。職人が手作業で採取する伝統技法ではなく、機械化に挑戦しています。沖縄工業高等専門学校の伊東繁名誉教授が開発した衝撃波破砕技術を活用しています。原木の細胞壁を衝撃波で壊し、圧搾して漆を抽出します。伝統技法では苗木を植えてから採取できるまで約15年かかります。職人が1本の木から採れるのは200グラムほどです。新しい破砕装置では5、6年の木での採取が可能で、1本当たり数倍の量を抽出できる見通しです。
また、確かな技術と品質を保証するために、地元の岩手県や二戸市(にのへし)と連携し、国産漆では初の認証マークを創設しました。その基準は、漆を採取する職人の技術、漆を採取する場所、不純物をいっさい加えない優れた品質の3点です。いずれも細部にいたるまで、詳しく、厳しく定められています。